作家たちが残した、パリについての「断章」
パリを題材にした小説やエッセー、ノンフィクションなどから、パリについて思いをはせたり、パリでの暮らしだったり、主人公が感じたパリというもの、などなど・・。
図書館や書棚の奥から引っ張り出してきた名著の中から、心に残るフレーズを見つけました。
「開高健のパリ 声の狩人」開高健
“Koe no Kariudo(The Hunter of Voices)” Takeshi Kaikō
ごぞんじのようにパリにはいたるところに広場がある。大きなのもあれば小さなのもある。・・・・パリ市の俯瞰図を見ると、複雑な血管の網のあちらこちらに大小さまざまな瘤ができたみたいである。
どれでもよいから一本の道をとって、たんねんにたどってゆくと、そのうちにきっとどこかで、この“丸い点〟に入る。昼でもたそがれたように薄暗い、しめってくたびれた壁のなかを歩いていると、 とつぜん石の腸のなかから広場へ踏みこむことになるのである。
この感じが好きだった。垢と時間で灰緑色に 錆びたような壁のなかから、 キャフェや肉屋や家具店などのキラキラ輝く赤、金、緑、黄、 黒、また、物音や、声や、香りの縞などにみたされた丸い井戸の底に入りこむ、このときの、華やかな不意の一撃の印象はたのしいものである。
~開高健「開高健のパリ 声の狩人」から
◆開高健(1930/昭和5 – 1989/昭和64・平成元)
小説家、随筆家。1954年(昭和29)寿屋(現サントリー)宣伝部を経て、広報誌「洋酒天国」の編集長を務める。1958(昭和33)年 「裸の王様」で第38回芥川賞を受賞した。以後『ベトナム戦記』(1965年)「フィッシュ・オン」(1974年)「地球はグラスのふちを回る」(1981年)など多数。


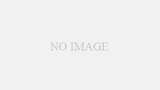
コメント