作家たちが残した、パリについての「断章」
パリを題材にした小説やエッセー、ノンフィクションなどから、パリについて思いをはせたり、パリでの暮らしだったり、主人公が感じたパリというもの、などなど・・。
図書館や書棚の奥から引っ張り出してきた名著の中から、心に残るフレーズを見つけました。
「開高健のパリ タケシのパリ(1967年)」開高健
“Takeshi no Pari(Takeshi’s Paris)”Takeshi Kaikō
パンテオンの正面のゆるい坂はスーフロ大通りである。
・・・パンテオンからちょっとさがってすぐ右へ折れたところに、スーフロ屋という小さな旅館があった。あとで人に教えられて、そこに荷風が泊っていたと知った。私もある年の夏に泊ったことがある。
・・・そのすぐ向いにマチュラン屋という小さな旅館がある。別の年の夏、またそのつぎの年の冬、そこに泊った。
・・・おかみさんは何も知らないけれど、この旅館のどこかの部屋に昔、リルケが下宿していた。そして、おそらく『マルテの手記』と思われる原稿を書いていた。夜遊びでくたびれたコクトーが青白い未明のなかをもどってくると、パンテオンをおりてすぐ右のある部屋の窓が、夜が明けたのにまだ灯を消さないで輝いている。
それを見てコクトーは考えるのだった。
「ああ。またリルケが痛がっている」
~開高健「開高健のパリ タケシのパリ(1967年)」から
◆開高健(1930/昭和5 – 1989/昭和64・平成元)
小説家、随筆家。1954年(昭和29)寿屋(現サントリー)宣伝部を経て、広報誌「洋酒天国」の編集長を務める。1958(昭和33)年 「裸の王様」で第38回芥川賞を受賞した。以後『ベトナム戦記』(1965年)「フィッシュ・オン」(1974年)「地球はグラスのふちを回る」(1981年)など多数。
小説家、随筆家。1954年(昭和29)寿屋(現サントリー)宣伝部を経て、広報誌「洋酒天国」の編集長を務める。1958(昭和33)年 「裸の王様」で第38回芥川賞を受賞した。以後『ベトナム戦記』(1965年)「フィッシュ・オン」(1974年)「地球はグラスのふちを回る」(1981年)など多数。


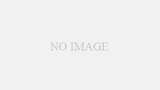
コメント