作家たちが残した、パリについての「断章」
パリを題材にした小説やエッセー、ノンフィクションなどから、パリについて思いをはせたり、パリでの暮らしだったり、主人公が感じたパリというもの、などなど・・。
図書館や書棚の奥から引っ張り出してきた名著の中から、心に残るフレーズを見つけました。
「パリ画信」荻須高徳
“PariGashin(Painting Report from Paris)” Takanori Oguiss
戰後の街頭風景戦前のパリしか知らないものに、パリにきて 最初に氣のつくことは、ヴォルテールの像はじめ数多くの銅像が、台座だけを残して消えていることである。これらは独軍占領中に兵器に姿を変えたのだという。パリの彫刻家は、再び新しい傑作をのせることを意気込んでいる。
しかし、ネイ將軍や、ロダンのバルザック像などは、そのままであり、石像にいたっては何の変りもない。階段や、橋の手すりまで、はずすような烈しいことは、ここではしてない。
バルザック像(左 ロダン美術館 右 モンパルナス)
冬のバリはまったく日が短い。私のように日中の光だけで絵を描く者はよほど緊張していないと、あっというまに一日の明るい時間がなくなってしまう。 朝の八時はまだ真暗だ。パン屋と牛乳屋と新聞屋ぐらいしかまだ店を開けていない。
九時 になってやっと明るくなる。それも霧か雨の日だったら十時になっても、否、終日うす暗い日がある。そして午後五時にはもう暗くなってしまう。
しかし正月がすぎると、たとえ寒い日がつづいていても、一日々々、びみょうな動きに日 は長くなる一方だし、明るい春に向う希望と楽しみがある。~荻須高徳「パリ画信」から

フランセーズ通り、パリ2区
◆荻須高徳(Takanori Oguiss 1901/明治34 -1986/昭和61)
稲沢市出身の洋画家。1926年に渡仏。1933年にはモンマルトルのオルドゥネ通りにある芸術家村「モンマルトル・オ・ザルティスト」にアトリエを構えるが1939年(昭和14年)戦況悪化のため一時帰国。戦後の1948年(昭和23年)に日本人画家として戦後初めてフランス入国を許可され再び渡仏。1986年、芸術家村「モンマルトル・オ・ザルティスト」のアトリエで亡くなるまでパリの風景などを数多く描いた。
「パリ画信」 は、1951年毎日新聞社から刊行された。
稲沢市出身の洋画家。1926年に渡仏。1933年にはモンマルトルのオルドゥネ通りにある芸術家村「モンマルトル・オ・ザルティスト」にアトリエを構えるが1939年(昭和14年)戦況悪化のため一時帰国。戦後の1948年(昭和23年)に日本人画家として戦後初めてフランス入国を許可され再び渡仏。1986年、芸術家村「モンマルトル・オ・ザルティスト」のアトリエで亡くなるまでパリの風景などを数多く描いた。
「パリ画信」 は、1951年毎日新聞社から刊行された。



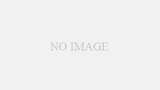
コメント