作家たちが残した、パリについての「断章」
パリを題材にした小説やエッセー、ノンフィクションなどから、パリについて思いをはせたり、パリでの暮らしだったり、主人公が感じたパリというもの、などなど・・。
図書館や書棚の奥から引っ張り出してきた名著の中から、心に残るフレーズを見つけました。
「パリの秘密 女魚屋の呼び声」鹿島茂
“Secrets of Paris” Shigeru kashima
魚屋というのは、なぜか昔から伝統的に女の職業とされていたのである。つまり、魚を売る商人といえば、それは即、女魚屋 (ポワソニエール)を意味していたのだ。
食肉屋が男の職業とさ れ、女が排除されていたのとは対照的である。 このことがよくわかるのは、パリの中央市場(レ・アール)を描いたエミール・ゾラの小説 『パリの胃袋』。とくに魚市場の描写に当てられている第三章を読むと、競りに参加しているの は女の魚屋ばかりであることが理解できる。男は競売係、記録係、それに運搬人などの裏方だけ。 ようするに、魚市場は、売り手も買い手もみんな女魚屋ばかりの「女の世界」なのである。
プルーストの『失われた時を求めて』にはさまざまな諧調の呼び声を発しながら街 を行商して歩く女魚屋の姿が捉えられている。 「小エビィ、おいしい小エビィ、生きのいいのを」 「揚げ物にタラァ、揚げ物にいかが」 「サバがまいりましたあ、生きのいいサバァ・・・・・・」(鈴木 道彦訳)
今度、ポワソニエールと名のつく通りを歩くことがあったら、一瞬、目を閉じて過去に思いを はせてみることをお勧めする。女魚屋の呼び声がどこからか聞こえてくるはずである
~鹿島茂「パリの秘密 女魚屋の呼び声」から
◆鹿島茂(Shigeru kashima 1949/昭和24 – )日本のフランス文学者。文芸評論家、翻訳家。19世紀フランス文学が専門。バルザック、ゾラ、ユーゴーら19世紀作家を題材にしたエッセイで知られる。1991年に 「馬車が買いたい!」でサントリー学芸賞受賞。19世紀フランスの希覯書を収集する古書マニアとしても有名。

レ・アール/Les Halles poissonnier 中央卸売市場の魚売り場 アジェ 1898年
1971年に取り壊され、その後跡地は巨大なショッピングセンターが建てられた。(Photo/BnF Gallica)


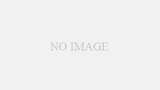
コメント