作家たちが残した、パリについての「断章」
パリを題材にした小説やエッセー、ノンフィクションなどから、パリについて思いをはせたり、パリでの暮らしだったり、主人公が感じたパリというもの、などなど・・。
図書館や書棚の奥から引っ張り出してきた名著の中から、心に残るフレーズを見つけました。
「パリ・スケッチブック」アーウィン・ショー
“Paris! Paris!” Irwin Shaw
ぽくがはじめてパりを見たのは一九四四年八月二十五日、つまりドイツ軍に占領されていたパリががようやく解放されたその日のことだ。
ぼくは第四師団第十二連隊に所属する通信隊の写真班にいた。・・・ぼくらのジープには切り花が山のように積みこんであった。パリへくる道筋の町や村の住民からのプレゼントだ。トマトやリンゴ、それに瓶詰のワインもけっこう積んでいた。街道に群がる人ごみをわけてそろそろとジープを進めてくると土地の住民が投げこんでくれたのだ。行く手をふさぐバリケードがあるとそれも住民がぶちこわしてくれた。パリ市内へ入ってようやくノートル・ダム大聖堂前の広場まで来てジープをとめた。すると、すぐ前のトラックに乗っていた兵土が一人、ノートル・ダムの塔をつくづく見上げてつぶやいた。「たった一月前はペンスンハーストにいたんだったなあ!」
~アーウィン・ショー「パリ・スケッチブック」から
◆アーウィン・ショー(Irwin Shaw 1913/大正2 – 1984年/昭和59)アメリカのの劇作家・小説家。1936年に戯曲「死者を葬れ」でデビューする。ファシズムの危機を警告した「ブルックリン神話」連作。1944年、「Walking Wounded」 でオー・ヘンリー賞受賞。1948年、第二次大戦における連合国とナチスの若者を描いた長編小説「若き獅子たち」(1958年映画化)。1970年には『リッチマン、プアマン』がベストセラーになる。「パリ・スケッチブック」は、パリ解放の日、米軍の報道班の一人としてパリに足を踏み入れ、その後四半世紀にわたり暮らしたパリの暮らしを綴った自伝的な随筆作品。

パリ 4区、ノートルダム大聖堂(2017年)
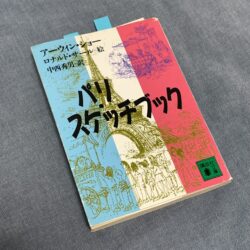
「パリ・スケッチブック」(1989年 講談社文庫)


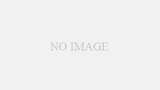
コメント