作家たちが残した、パリについての「断章」
パリを題材にした小説やエッセー、ノンフィクションなどから、パリについて思いをはせたり、パリでの暮らしだったり、主人公が感じたパリというもの、などなど・・。
図書館や書棚の奥から引っ張り出してきた名著の中から、心に残るフレーズを見つけました。
「ルーアンの丘」遠藤周作
“Rouen no Oka(Hill of Rouen)” Endō Shūsaku
10月9日(木)
巴里は今一番美しい金色に包まれている。巴里の秋の空は青くもなく黒くもない。淡い淋しい日の光が午後から消えたり照ったりする。マロニエの葉は歩道一杯をしきつめている。
・・・メトロの中で、ぼくはふとマルテの事を思い出した。マルテは巴里で死に脅かされていた。ぼくも病に脅かされつつ巴里の街を歩いている。しかし、生きねならない。
12月29日(月)
しかし今日、ジュリエット・グレコが病院に歌いに来てくれた・・・。彼女の金色の髪は肩までたれ、その表情は石のように冷たい。虚無的な声で、歌った。如何にもサンジェルマン・デ・プレの虚無を心えた女である。甘い、やさしい虚無、うその虚無・・・そのあとでダンスパーティがあった。
~遠藤周作「ルーアンの丘」から
◆遠藤周作(1923/大正12 – 1996/平成8)小説家、随筆家。父親の仕事の都合で幼少時代を満洲で過ごし、帰国後の12歳の時にカトリック夙川教会で洗礼を受ける。生涯、キリスト教を主題にした作品を多く執筆。1955年「白い人」で芥川賞を受賞。小説家として脚光を浴びた。
1950年(昭和25年)フランスのリヨンに留学。1998年、没後発見された未発表のエッセイと日記その当時の日常が「ルーアンの丘」にまとめられた。


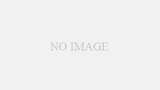
コメント